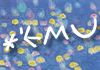|
■ おばけ地下鉄
◆ 何かがやってくる
小学五年生の夏休みの出来事である。
「何かがやってくる!」
ボクは身を堅くした。信号の色が変わる。
「地下鉄に決まってるじゃないか」
そう、ここは地下鉄のホーム。他に何がくるというのだ。それなのに、ボクの膝はこわばり、背中の汗が冷たくなった。
「ごうっ」
迫りくる風圧に髪の毛が流れ、汗ばんだ顔にまとわりつく。
「きいいん!」
金属が軋む音。やがて暗闇から姿が現れる。ボクは半円形のトンネルの奥を見つめた。瞬間、ふたつの発光がボクの目に届く。けれども、それは地下鉄のライトではない。
「また、あいつがやってくる!」
ギラギラと輝く複眼。いくつもに区切られた胴体のいちいちで動く足の群れ。それら先端で鋭い鉤爪が線路を引っ掻き、嫌な音をたてている。
「逃げなくては…」
ムカデの化け物は目前に迫っていた。でも、動けない。複眼の魔力で手足が金縛りにかかっている。それに、ここは地下世界だ。手足が自由になったとしても、飛んで逃げることは不可能なのだ。
「助けて」
でも、声にならない。ボクは無人の地下ホームで途方に暮れていた。
◆ 帰りは違う駅
1959年、夏。蝉時雨に見上げれば、ボクを圧倒して伏魔殿がそびえている。その次の年、ここを舞台にした安保闘争の騒乱の中、ひとりの女子大生が亡くなることなど、そのときのボクが知るはずもなかった。
国会議事堂と東京駅を初めて見たときの驚きを忘れられないでいる。大きかった。とにかく大きかった。そして、大きさは理屈を超越して人間を変容させる。威圧し、屈服させ、やがては乗り越えさせようとする。山があるから人は登る。海があるから人は渡る。それがいかなる単位であっても、物理的な大きさは精神宇宙では常に有限であって、その優位性を人間に保持することができない。人間の大きさを測るのは物差しではなく、心差し(こころざし)なのである。
帰宅するには国家の権威を大きさで象徴しようと設計された建物を、はるばる通過していかねばならない。中がどうなっているのかに興味はなかった。けれども、そのシンメトリカルな形状は、政治のシステムと関係があるに違いないとは感じていた。二院制を理解はしていなかったが、ボクにとって正しくシンメトリカルであることは、歩いた距離の物差しにはなってくれた。つまり、構造物の形状は退屈しのぎという役割を果たしてくれたのだ。
「今日も言葉を交わせなかった」
目を閉じれば、網膜に焼き付けられた黒い瞳、夏の妖精。25メートルの波打つプール。けれども、どれだけクロールを頑張っても、黒い瞳との距離を縮めることはできないのだ。
背中のナップザックには濡れた水泳パンツ。その目方よりも重い心を引きずりながらボクは足を運んでいた。気分を変えたい。そう考えて、帰りは別の道を選んだのである。
「エマウドジギイカッコ、エマウドジギイカッコ」
口の中で繰り返す呪文。
「ケツミカサカア、エマウドジギイカッコ、キセガミスカ、ザンギシニ」
この呪文を、ボクは大人になっても忘れることはないだろう。
「ケツミカサカア、エマウドジギイカッコ、キセガミスカ、ザンギシニ」
呪文を繰り返すボクを大理石の伏魔殿が見下ろしている。やがて建物は終わり、ボクは角を曲がった。
地下への入り口を降りると、静かに機会が動いている。
「ごとん、ごとん」
エスカレーターの無限階段が現れては消える。その繰り返しのアナウンスがボクの頭で反響した。
「国会議事堂前、国会議事堂前」
改札口で定期券をちらつかせると、駅員はそれには目もくれず、魚のような瞳でボクの顔を見つめた。その視線を背中に感じながら、ホームへ降りる。誰もいない。ただ、灰皿でくすぶる消し忘れのタバコが、フィルターの化学繊維を焦がして、嫌な匂いを周囲に発散させていた。
◆ ふたつの地下鉄
丸の内線は新しい地下鉄だった。銀座線が黄色の車体であるのに対して、丸の内線のボディーは赤い。そして銀色に輝く飾りがその新しさを強調していた。
1959年5月、父親の転勤で我が家族は引越しをした。新宿区戸塚町三丁目から千代田区内幸町一丁目への民族大移動だった。心残りはふたつだけ、番犬のクロと壁の鞍馬天狗を連れていけなかったことである。いずれにせよ、社宅から社宅への移転であって、どちらも東京電力の変電所の敷地内であることに違いはなかった。
「ぶううん」
どこからともなく低い振動音。変圧器の唸りである。そして、水冷にせよ、空冷いせよ、変電所は常に変圧器からの熱を発生させていた。
「ぶううん」
夏ともなれば、蚊帳の中でその音を聞く。蚊が飛んでいるのではなく、変圧器が24時間無休で働いているのである。変電所の発するハム音と温水や温風は、ボクの育った環境であった。
住所が変われば小学校も変わる。ボクは新宿区戸塚第三小学校から千代田区立永田町小学校へ転校した。距離的なことをいえば、すぐ目の前に岱明小学校があるのだが、国鉄の線路を隔てた向かいは中央区であって、ボクは入学を許されなかったのだ。
◆ 地面の下
地面の下はどうなっているのだろう。小学校の図書館で『地底探検』という本を読んだことがあった。地底には別世界があり、そこには湖や森があって、失われた生き物たちがいる。そんな内容だったと思う。同じようなテーマで映画もいろいろと作られていて、その何本かは見ている。頭に巨大なドリルをつけたロケットで、無理やりに地面を掘削して潜り込んでいくようなSFだったり、もっとプリミティブな探検物語だったりして、古代の恐竜みたいな生き物が現れたり、地底人と闘ったりと、いろいろな映画が頭の中でミックスされて、ゴチャゴチャになっている。
小さかった頃、防空壕という単語をやたらと耳にした。祖母のいた柳沢には1トン爆弾の穴が点在していて、大きく口を開けていた。それを見ていると、地面を掘るのは難しいことではないと思えた。地面の下を見てみたい。これは水の中をのぞきたい願望と同じくらい根深いものだった。
ヤマグチ君の庭で、番犬が大きく穴を掘った。どんどん掘り下げて、その茶色いイヌの全身が潜ってしまうほどになっていく。どれだけの穴になるのか楽しみで、ボクはそのイヌを応援した。もしかしたら、ボクの地底探検の入り口になるかもしれないと考えたのだ。けれども、家が傾くことを恐れたヤマグチ君のお父さんが穴を埋めてしまい、ボクの地底探検の夢も消えうせた。
そこで自分の庭を掘ってみる。シャベルやスコップで掘るのだが、地面が違うのか、やたらと水が出てきて、すぐに穴が水浸しになってしまう。その穴掘りを見ていた父親は、庭の真ん中に池を作った。春になると、その池にカエルが集まり、水面が見えなくなるほど産卵をして、やがて池はオタマジャクシで真っ黒になった。
その頃のボクは、やたらに化石が欲しくて仕方がなかった。岩石と岩石の間から出現する化石に魅了されていた。そこで化石を創ろうと決心する。ボクは晩御飯のおかずの秋刀魚の骨を、家族に内緒で地面に埋めた。平らな石と石で骨をサンドウィッチにして埋めた。その骨が化石になったかどうかは、引越しをしてしまったので確認はしていないが、何万年かして、未来人がボクの代わりに発掘してくれるかもしれない。
引越しは秋刀魚の化石をボクから奪ってしまったが、地下鉄通学は、ボクの地底探検の夢をひとつの形にしてくれたといえる。
◆ ふたつの駅にはさまれて
永田町小学校の記章は国会議事堂である。つまり、議事堂の方が先にできたのである。これは議事堂で議論するまでもない。それでも議事堂は目立ちたいのか、高い場所で威張っている。そして、小学校も坂の頂点に立っていた。
地下鉄赤坂見附駅から小学校までは上り坂。そして国会議事堂前までは平坦な道。ということは、ふたつの駅は勾配で結ばれているのだろうか。
道路から考えても丸の内線新宿駅から四ッ谷駅までは新宿通りの下をストレートでくればよい。ところが、四谷から赤坂見附までは、ぐうんと右折して坂を下る。これは地下鉄に乗っていても感じることである。そして赤坂見附で丸の内線と銀座線が出会う。ここから共通する目的地が銀座なのである。けれども、銀座線は名前の通り、銀座駅。そして新顔の丸の内線は、有楽町や日比谷に近い西銀座駅を目指すのだ。銀座と西銀座。銀座という大都会東京を象徴する拠点を通過すれば、古顔の銀座線は伝統ある繁華街の浅草を終着駅とする。そして新顔の丸の内線は山手線ならたった五駅の池袋を終着駅としたのである。つまり、丸の内線は、この赤坂見附で進路変更して、ぐるりとヘアピンのように曲がるのである。
東銀座ができたせいか、現在は西銀座も銀座も同じ銀座に統一されてしまった。歩けばちょいとした距離ではあるが、この乗り換え時間を無視して、あたかも同じ駅であるかのごとくに知らしめている。地下鉄の駅名にはこのトリックが多い。路線図でダマされてはいけない。同じ駅のようで、同じホームでないのだ。ついついこいつを忘れて、簡単に乗り換えられると思うと、同じ駅名の間をとぼとぼと歩かされる羽目になる。
◆ 半円形のトンネル
国会議事堂は丸の内線の駅として、ひとつの特徴を有している。つまり、この地下ホームに立って赤坂見附方面を見ると、ここだけが半円形のトンネルをしているのだ。通常、地下鉄のトンネルは四角い。なのに、国会議事堂前だけは特別なトンネル構造になっていて、これが不思議でならなかった。上に議事堂や首相官邸があるから、この地下には特殊な防空壕とか秘密指令基地があって、それで他とは違うのかな、なんて東宝の特撮映画の影響を強く受けている自分としては、なんとなくSFチックなき分になったものである。
だから、ホームにひとり立つとき、不可思議な幻想に心を奪われてしまうのかもしれないし、または幻を現実と感じてしまうのかもしれなかった。
けれども、日常に非日常を見るとき、ボクは恍惚となる。これぞ真実と踊りたくなる。当たり前の舞台で普通に語り、歩いていた登場人物が、いきなり歌い、ステップを踏んで踊りだして、ミュージカルが始まるように、ボクの心もワンダーランドに突入するのである。
1959年当時の国会議事堂駅前はボクのワンダーランドの入り口だったのかもしれない。ムカデでもなく、蒸気機関車でもなく、乗合馬車でも、幽霊船でもない、当たり前の赤い電車に乗って、ボクは西銀座へと運ばれる。
「きいいん、きいいん」
車輪と線路の軋む音に身を委ねながら、繰り返す呪文。
「ケツミカサカア、エマウドジギイカッコ、キセガミスカ、ザンギシニ」
目の前の闇の世界で、跳ねては踊り、現れては消えるシグナルや電線。速度が鈍れば蛍光灯の明るさ。その繰り返しがボクを家へ連れていく。赤坂見附、国会議事堂前、霞ヶ関、西銀座。
自分の未来で、この手が「じめんのした」や「おばけちかてつ」などという絵本を誕生させることなど夢にも思わず、ボクはナップザックの中の濡れた水泳パンツを、洗濯機に突っ込もうか、それとも手洗いをしておこうかと、真剣に悩むのだった。
2008年4月、永田町小学校最後の同窓会が開かれた。廃校になってから久しい。けれども、建物は麹町小学校の臨時校舎として、その使命を果たしてきた。これからも、麹町中学の臨時校舎としての役割が期待されている。しかし、いつかこの歴史的建造物も地上から消滅する運命にあると聞く。けれども、ボクら卒業生は、政治の喧騒の中に黙して立つ、この歴史ある建造物に新しい役割が与えられ、いつまでもその雄姿を坂の頂上にとどめることを心から祈っている。
2008/08/23
|