 |
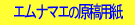 |
|
||
|
||
|
|
||
| |
| ◆ 「ラジオ世界」 エム ナマエ 思い出す、あの懐かしいラジオドラマ。そして、焼け跡の空き地。日の暮れまで夢中で遊んでいると、いきなり垣根の向こうから、あのテーマソングが耳に飛びこんでくる。遊び仲間は一瞬だけ顔を見合わせると、蜘蛛の子を散らすように解散した。ぼくも慌てて家へ走って帰る。間一髪のセーフ。玄関を入ると、煮物や味噌汁の湯気の香りで、いつものようにラジオが歌っていた。大好きなテーマソングが終ると、いよいよ昨日の続きだ。ついさっきまで空き地のカウボーイだったぼくは、もうラジオの前で少年探偵団の一員になりきっていた。 落語や浪曲は祖母と聴いた。ラジオドラマは弟と聴いた。クイズ番組は家族で聴いた。父親は隣人のためのラジオ工作をしながら、母親はセーターを編みながら、そして祖母は針仕事をしつつ、ラジオに耳を傾けていた。おそらくは、それぞれの映像を心に浮かべて。 中村メイコって、どんなに素敵なお姉さんなんだろう。黒柳徹子って、きっと奇麗な人だぞ。ラジオからの声は、ぼくに無限の想像を与えてくれた。ラジオは絵本やマンガでは味わうことのできない憧れ、もうひとつの世界への扉だった。 よちよち歩きの頃から、ぼくは父親に連れられて週に数本の映画を見せられていた。白黒あり、天然色あり。西部劇にチャンバラ、記録映画やミュージカル。わくわくする映像、退屈な物語。そして、そのいずれもが別世界への大きな窓だった。しかし、我が家に青白い顔の小さな窓が出現した。やがて父親は映画館には通わなくなり、畳に寝転がって四角い画面へ釘付けとなる。そして、いつか茶の間からラジオの声が消えていた。 いつの頃からか、我が家の食卓に透明人間の座席が確保されるようになった。みんな、食べ物を口に運びながら、見えない客人から目が離せないでいる。いつも、その不思議な客人はテレビに背中を向けて座っていた。 テレビは映画も見せてくれた。相撲も野球も見せてくれた。ラジオで憧れていた人物の顔も見せてくれた。ただ座っているだけで、チャンネルを回すだけで、自分はどこにでもいけて何でも見られるような気になっていた。 トランジスタラジオと高校受験。彼等がぼくに深夜放送を教えてくれる。机の前の若き魂と、机の上のポータブルラジオが共鳴して、しおれかかった想像力に水が注がれたのだ。これが、ぼくとラジオとの再会だった。 イラストレーターとなってからの情報は、専らラジオからであった。アイディアやインスピレーションは言葉によって触発される。とはいえ、画家であるからには映像による情報も不可欠だ。本棚には図鑑や写真集。壁一面には映画のビディオ。映画マニアだったぼくは映画ビディオのコレクションに夢中になっていたのだ。しかし、テレビの四角い画面には限界があり、虚構があった。ぼくは誰かの意図により箱詰めされた映像よりは本物を求めて旅に出た。博物館や美術館も訪れた。広い世界と実物を目前にして、自ら写真を撮影し、ムービーカメラを回した。だが、それらの行為により撮影された映像はフィルムにではなく、自分の記憶に焼き付けられていた。それらが唯一の財産になるとも知らずに。 現在、ぼくは全盲である。そして画家でもある。ぼくは失明を境界線にして、職業も生き方も変えてはいない。変わったのはただ、目が見えなくなったという事実だけだ。 我が家のすべての部屋にラジオがある。風呂場にも防水ラジオ。移動するときはポケットのラジオを聴く。勿論、外出するときもラジオは忘れない。それは自分が盲人だからではない。失明以前からラジオは最も大切な友人だった。そこには本物の人間が暮らしている。そして、ラジオは四角く区切られた情報ではなく、出来事の言葉による認識を宇宙的視野で伝えてくれるのだ。 失明直後は見たいという欲望に振り回され、見られないという絶望に心身を焼かれたりもした。だが、やがて気がつく。これはラジオの世界なのだと。見えないことに慣れさえすれば、コンピューターによる執筆も、絵を描くことも当たり前の行為となる。創作世界の住人でありさえすれば、見えない不便とは無縁でいられるのだ。そして周囲はラジオの世界。すべての音が自分に最も理想的な映像を与えてくれる。優れた文学作品による自分だけのイメージを、不出来な脚本や映像とミスキャストの映画で失望させられることもない。ぼくは見える不自由から解放されたのである。 同じ絵でも、観賞者によって印象は違う。同じ物を見ても、人によって見方が異なる。同じ街でも、人は別々の物を求める。大切なのは、それがどう見えるかではなく、それをどう見るかだ。そして、どれもが正解であり、どれもが間違いでもある。ラジオからのメッセージに、どんな映像を浮かべるか。ラジオ世界は人生のスクリーンかもしれない。 |
 |
| Copyright © emunamae |  |
|