 |
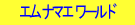 |
|
||
|
||
|
|
||
 |
| -
どうしてボクは絵をかくのか - どうしてボクは絵をかくのだろう。それはボクが画家だから。そう答えるしかない。こうして文章を書いていても、頭の中は絵の世界。いろいろな形や顔が見えている。あふれる色彩が見えてくる。ときどきは、それをどうしても絵という形にしてみたくなってしまうのだ。たとえボクが盲目でも。 失明してすぐ、ボクに絵をかくことは可能だと思った。それは、当時のボクが自分では読むことのできない文字で物語を書いていたからだ。ボクに見ることのできない文字。でも、他の人には読んでもらえる文字。それは、盲目のボクの書く文字が、文字になっていたからである。幼い頃、文字というものを覚えてから、いつもずっと書いてきた文字たちだ。見なくたって書けるに決まっている。誰だって目を閉じても自分の名前くらいは正確に書くことができるはずである。嘘だと思ったら、やってみるといい。ほうら、ちゃんとできるでしょう。もともとボクは文章を書くことが好きだったから、いつも文字を書いていた。だから盲目になってからも点字でない普通の文字で物語を書き始めた。それができるなら、絵も同じ理由でかけるに違いない。そう感じた。だが、やる気にはなれなかった。それは職業画家だったボクがやるには、あまりにも無責任な行為に思えたと同時に、自分に見ることのできない自分の絵など、まるで興味がなかったからだ。 だが、それを自分にさせるときがきた。ほんの悪戯でかいた絵を婚約者だったコボちゃんが喜んでくれたからだ。彼女だけではない。見せる人、見せる人がそれなりの評価をしてくれる。ボクの絵に価値を認めてくれたのだ。ボクには見えなくとも、人がボクの絵を楽しんでいる。もう、それだけで充分だった。ボクは一気に絵をかき出した。そしてやがて展覧会の依頼がくる。ボクの人生が大きく方向転換する事件だった。 盲目で恒常的に美術作品を提供する技術。これをマスターしなければならない。ボクは試行錯誤を連続した。自分のドローイングを確認するために、製図ペンをボールペンに持ち換える。力強くかけば痕跡の残るボールペン。これで、ある程度正確な描線を引くことができた。 ここで誤解を招かないため、あえて生意気と受け取られることを覚悟して書くことにしよう。誰でもボールペンさえあれば、目を閉じて絵をかくことができるわけではない。ボクにそれが可能なのは、ボクが経験を積んだイラストレーターだからである。無数の形と直線曲線。これらを自由自在に描いてきたからこそ可能な業なのだ。よく誤解されるのは、ボクがボールペンの奇跡をなぞって絵をかいていると思われることだ。そうではない。どんなにボールペンの奇跡を指先でなぞって見ても、そこに形が見えてくるわけではない。そんなこと、中途失明のボクにはとても不可能だ。要するに、ペンの奇跡はボクのドローイングの当たりでしかない。つまり、失敗しないための当たりである。はみ出しや重なりを阻止するためのテクニックである。この当たりさえつかんでいれば、大きな間違いを心配せずに、真っ黒な描線で下絵を作ることができる。それだけのためのボールペンであり、肝心なのはボクの手と指先が頭脳と直結している事実である。頭に絵が浮かぶと自然に手が動き、絵ができてしまうのだ。正直に告白すると、ボクにとって盲目で絵をかくことは、何の苦労も必要としない簡単至極な芸当なのだ。 では、どうやって彩色していくか。これが第二の問題であって、ここからが本格的な試行錯誤となった。油絵、水彩、カラーインク。アクリル、パステル、水墨画。プロのイラストレーターとなってからも、ありとあらゆるテクニックを試してきた。勿論、独学によってである。ボクは学校の図工や美術の授業以外、誰からも絵の指導を受けたことがない。ただひたすら、絵をやりたい気持ちだけで、考えられる技法のすべてを独学で身につけた。今こそ、この見えない目で、それらを試してみるのだ。 アクリル絵の具による盛り上がりで制作すれば、かなり面白い絵ができることがわかった。しかし、これはあまりに時間がかかる。いい絵はできても、プロとしては現実的な手法とはいえない。しかし、得意だった水彩やカラーインクで表現するには、柔らかい筆と水をコントロールするのに、盲目というハンディキャップはあまりに大き過ぎた。だが、水彩やカラーインクのボカシ技法で色と画面を構成したい。そこで思いついたのがパステルによるボカシである。パステルなら水も筆も必要としない。指先から伝わる感覚だけで彩色作業が可能だ。それに使い慣れた特定メーカーのパステルもある。早速、このパステルで一枚を完成させた。手応えもいい。評判もいい。これだ。これに決めた。この技法で今後の絵画制作をしていこう。 下絵を制作しているときから、既に色彩構成が見えている。そのプロセスもわかっている。後は誰かの手を借りて、それらを実行に移すだけなのだ。 絶対音感というものがある。そして色彩にもそれと同じ絶対色感というものがあるに違いない。ボクの場合がそれなのだ。ゆらぎのない色彩感覚。一度使用した絵の具の色を完璧なほどに記憶していて、それが薄らいだり忘れてしまうことがない。その記憶と色彩理論で構成すれば、考えている通りの絵ができるはずなのだ。あとは絵の具を間違えないこと。そこでサポートが必要となる。しかし、手を貸してくれるのが絵のプロフェッショナルとは限らない。さて、どうするか。ここで都合がよかったのは、ボクの使用するパステルには番号が刻印されていることだった。ボクが色の名前を告げる。レモンイエロー、オーレオリン、バーミリオン、オキサイドオブクロニウム、ウォームグレイ、パーマネントイエロー、インディゴ、カーマイン、パープル、ウルトラマリン、エメラルドグリーン、スカイブルー、イエローオーカー、バーントシエナ、セピア、ビリジャン、ラベンダー、マゼンタ、ボルドー、クリムソン、コバルトブルー、コーラルレッド。協力者はその名前を色彩一覧表に求める。その名前を発見すると、それに指定されている番号を確認する。そして、百五十色のパステルセットから、この番号を探すのだ。素人にはかなり苦労の作業である。自分だったら一目でわかることを、何分間も待たなければならない。これがボクにとっては最も忍耐の必要な過程なのだ。さあ、やっと絵の具が見つかった。そして、そのパステルを持たせてもらい、彩色したい場所へ導いてもらうのである。そこからは簡単。適当にゴシゴシやって、それを布や紙でぼかしてしまう。これを重ねれば、いつの間にか一枚の絵ができあがるのだ。 現在は家内のコボちゃんがこれをやっている。もう十年もやっているから少しは慣れた。だが、彼女はずぶの素人で、おまけに記憶力が危ういので、今でもかなり苦労してパステルを選んでいる。だが、それでいい。もしも彼女が絵のプロであったら、ボクの彩色に意見をいい、あれこれアドバイスをするだろう。それはボクにとって一種の縛りとなる。盲目であるからこその自由が許されてもいいはずだ。ボクはどこまでも自由に、そして自らの判断を信じて絵を制作する。それがいちばん楽しいのだ。そして、ボクの目の中ではなく、観賞者の目の中でボクの絵が完成することこそ、ボクの絵の最大の価値なのだ。 2001/02/03 エム ナマエ |
| Copyright © emunamae |  |
|