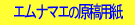|
◆ ここに全盲のイラストレーターが存在する
ぼくは自分を全盲のイラストレーターと呼んでいるが、障害を売り物にするつもりはない。イラストレーターとしての充分な経験さえあれば、中途失明者だって職業画家としての道は開けるはずだ。だが、目が見えなければ絵は駄目という一般的常識がある。クリアーすべきはこの常識という障壁であって、障害が障壁となっているわけではない。中途障害者の未来は、ひたすら当人の自覚と自己決定に委ねられている。結果を作ることによって新しい職業領域の可能性を示したい。だからぼくは全盲のイラストレーターという肩書きにこだわるのだ。
でも、自分の作品を見ることができないことくらい、画家にとってつまらないこともない。だから、ぼくは画家から作家に転身した。表現者として生きる以上、自分の作品を楽しみたい。目が見えなくなっても、自分の作品が文章だったら誰かに朗読してもらえる。失明したぼくが一度はイラストレーターを捨てた理由がこれだった。
でも失明してから四年、ぼくはイラストレーターとして復活した。ぼくの絵を楽しんでくれる人がいたからだ。最初は妻。それから友人。そして展覧会のお客さん。ぼくの絵は見てくれる人の目の中で完成する。自分には見えない作品でも、喜んでくれる人さえいればそれでいい。こうしてぼくは再び画家となり、最近では多様なメディアによって、ぼくの絵は広く知られるようになってきた。
◆ 見る目を失ったニッポン
しかし、ほんの小数の熱烈な支持者によって、ぼくの生活は支えられている。これが現状だ。というのも、イラストレーター本来の仕事があまり多くはないからである。個人は認めてくれても、クライアントとしての企業がなかなか認めてくれない。ちょっと頑張っている障害者。失った機能のリハビリテーション。ここに歴史上最初の全盲のイラストレーターが存在するというのに、ニッポンでは大勢の見方がこれなのだ。
障害は単なる事実であって、それ以上でもそれ以下でもない。だから、画家の目が見えないからとて作品に付加価値が生まれるとは思わない。もしも音楽家が全盲を理由にもてはやされたとしたら、それは単なる特別扱いであって正当な評価とはいえないだろう。ポイントはその仕事が報酬に価するかどうかだ。1990年以来、全盲のイラストレーターとして仕事をしてきたぼくの実感がこれである。
盲人が絵を描く面白さや物珍しさだけで、その作品を高価で購入する人はいないだろう。同じ人物が何枚もぼくの作品を所有している実例は、所有者がその作品に魅力と価値を感じている証拠だ。ぼくの作品はその人の部屋の壁で、確実な仕事をしているのだ。光を放っているのだ。
しかし、オリジナルの絵はたった一枚しか存在しない。そしてイラストレーションは複製されてこそ真価を発揮する。ぼくの作品の光は、その作品を必要とする魂の数だけ増幅されるべきだ。しかし、個人には限界がある。やはり力のあるクライアントが必要なのだ。しかも、自立した目と独立した精神を有するクライアントが。バブル崩壊後の自信を失い、見る目を失ったニッポン。ぼくには「自主独立」という価値を実現しているどこかの国で、自分の作品が評価されるという確信があった。
ニッポンにはお金の使い方を知らない企業が多い気がする。政府も同様だ。その証拠にモモタロウが鬼の宝をどう使ったのか、日本人はあまり興味を示さない。金持ちになった民話の主人公はいろいろといても、その金銭哲学についてはほとんど書かれていない。戦後のニッポンでは目的としての金はあっても、手段としての金は存在してこなかった。だからニッポンはバブルに踊り、バブルに泣いた。不安と貯金を抱えたニッポンはいまだバブル崩壊の後遺症から脱出できないでいる。国が税金を正しく使わなければ、消費税はただ景気のブレーキとしかならない。そして最大の悲劇は、方向を失ったニッポンを動かしているのが「外圧」という事実である。
◆ ブラックホール、ニューヨーク
一九八〇年、ニューヨークはぼくにとって特別な場所となった。ジョンレノンの暗殺。その瞬間からニューヨークわぼくに向かって強大な引力を発した。ジョンが愛した自由と独立の都会、ニューヨークへいきたい。だが、1983年、ぼくは失明を宣告され、その三年後に全盲となり人工透析を導入した。それ以来、ニューヨークへの道は閉ざされたとぼくは思いこんでいた。
画家に復活したぼくは、いつの頃からかニューヨークで個展を開きたいと願うようになっていた。弱肉強食の都会で、ぼくの作品がどのような光を放つのか。自主独立の精神はぼくの作品をどう評価するのか。そのことに興味があった。いや、ニューヨークが認めてくれないのなら、どこで個展を開いても無駄だろう。世界の欲望と希望の箱庭、ニューヨーク。ぼくの作品に真実の光があるのなら、必ず引き寄せられる魂があるはずだ。いつか、そのチャンスに賭けてみよう。ぼくは盲導犬使用者と透析患者というリスクを道連れにして、ニューヨークへの旅立ちを決心した。
◆ ホテル・エセックスハウス、セントラルパークルーム
友人が金を貸してくれた。理解者がカンパをしてくれた。JALがサポートしてくれた。おかげでニューヨークはセントラルパークの南、エセックスハウスという高級ホテルでの個展が実現したのだ。
セントラルパークに面してダコタハウスというアパートがある。ジョンレノンはここに暮らしていた。ぼくにとってセントラルパークは特別な場所なのだ。そして、エセックスハウスもセントラルパークに面していた。ひとつの点がぼくを引き寄せる。ギャラリーを持たないエセックスハウスがJALの配慮で個展のために用意してくれたのもセントラルパークルームという宴会場だった。偶然にはサインがある。ぼくはこの符号に意味を感じていた。何かが始まる。出発前から予感は強くなる。ぼくは一枚の絵をサムソナイトに忍ばせた。それは失明後最初の版画、イメージ・ジョンレノンだった。
ニューヨークは雨でぼくと妻と盲導犬アリーナを迎えた。しかし、美しい日曜日がぼくらを待ってくれていたのだ。晴天のセントラルパーク。ローラーブレードの若者達。ホットドッグ。散歩の犬。ニューヨークのビュウティフルサンデイはぼくらを夢中にさせた。そして、気がつくとダコタハウスの前に立っていたのだ。一瞬にして、ぼくは一九八〇年のあの瞬間に逆戻りしていた。涙があふれてくる。ぼくはあの瞬間に決意したのだ。ジョンの仕事の百万分の一でも引き継ぎたいと。
ジョンのメモリアル、ストロベリーフィールズにはギターや沢山の花束が捧げられていた。二日前はジョンの誕生日だったのだ。またしても偶然がぼくのハートを揺さぶる。そしてこの日、十月十一日は妻とのデート記念日であり、ぼくの画家復活の原点だった。そして明日からニューヨーク個展が始まるのだ。
◆ ジョンの魂
日本からの友人達、在ニューヨークのボランティアのおかげで個展は無事スタートした。作品は自薦の五十八点。セントラルパークルームは花園になったと友人達は賛美してくれた。在米邦人もニューヨーカーもぼくの作品を評価してくれる。しかし、クライアントとなるべき企業がまるで現れない。個人で開いた展覧会である。スポンサーもなければ宣伝もない。だから、それはそれで当然の結果かもしれない。しかし、自由の女神のニューヨークで幸運の女神に遭遇するのは、ほんの一握りの人間にしか許されない奇跡なのだと改めて実感していた。
「スゴい人が現れましたよ」
人工透析から帰った深夜。ホテルの玄関で個展準備委員会長、ジャーナリストの下村健一氏が興奮を抑えた口調で伝える。偶然にもある人物がこのホテルに宿泊していて、偶然にも個展のポスターを目にした。そして会場に現れたのだ。その人物は全米最大の子供服メーカーの幹部だった。
真心で祈るとき、不思議な偶然が訪れる。このメーカーはジョンレノンの未発表の絵画を子供服のデザインとしてリリースしようとしていた矢先だったのだ。そのおかげで、彼を通じてぼくの版画はヨーコオノに手渡されることになった。画家に復活して以来の念願が実現したのだ。そればかりではない。会社はクライアントとしてぼくの作品を評価してくれたのだ。帰国してしばらく、正式のオファーがあった。ぼくの絵が子供服になる。それもジョンの魂の導きで。ついにドラマは始まったのだ。
※ 1999年 週刊金曜日 掲載
|