 |
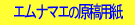 |
|
||
|
||
|
|
||
| |
| ◆ 海岸の考古学者 湿った風が砂丘を渡り、「海」の香りを運んできます。 「かあさん。ちょっと、いってくる」 「また、あの男の所かい」 母親は台所仕事の手を休めると、勝手口から早朝の光の中へ走り出ようとしている少年の肩ごしに声をかけました。 「ああ…。いけないかい」 少年はピタリと動きをとめました。 「あんな男の、どこがいいんだろうねえ。まさか、おまえ…。あんな変わり者のおしゃべりなんか、信じてやしないだろうね」 少年はドアノブを握ったまま、ちらりと母親の横顔をのぞきました。 「そんな心配いらないよ、かあさん。それに、エム氏は変わり者なんかじゃない。立派な考古学者だよ」 「どこが学者なもんか。第一、こんな砂ばかりの土地で何を研究してるのさ」 少年は開きかけていたドアを引き寄せ、わざと音をたてて閉め直すと、母親を振り返り、一気にしゃべりました。 「エム氏はね、蜃気楼の化石を発掘して、調査してるのさ。立派な研究だよ」 「蜃気楼の化石だって…。馬鹿馬鹿しい」 「…」 少年はしゃべってしまったことを後悔するように黙りこんでしまいました。 「蜃気楼って、何のさ?」 「…」 「ほうら、いえやしないじゃないか。そんなの、デタラメだからさ」 「デタラメなんかじゃないよ」 少年は、はじかれたように叫びました。 「ここいらは、記憶の砂粒がいくらでも見つかるんだ。エム氏はそれを集めて、あの古い熔鉱炉で溶かして、化石に結晶させてるんだ。かあさんだって、蜃気楼の化石を見れば信じるさ」 母親は、ひとつ肩をすくめました。 「わたしゃ、このあたりの海で蜃気楼を見たなんて、聞いたことないけどねえ…」 「そりゃ、そうさ。だって、それはずっと昔の話だもの。ずっと、ずっと昔の話だもの。だから化石になってるんじゃないか。どんな物だって、化石になるには気の遠くなるような時間が必要だって、エム氏もいってるよ。それに、時間も一種の熔鉱炉なんだってさ」 「…」 「今じゃ、ここいらは砂ばかりだけれど、大昔、このあたりにはスゴイ文明があったんだ。無数の星をちりばめた天まで届くような塔がひしめく大都市があって、巨大な浮かぶ船の出入りする港もあったんだ。ここの砂粒は、みんなその証拠なんだって」 「本当にあったもんなら、どうして蜃気楼だなんていうんだい?」 「だからさ、だから、その古代文明がある日、いきなり壊れて消えちゃったんだ。砂粒はその証拠だって、ぼく、いったろう。それでね、それで、その頃まだ元気だった海がそれを覚えていて、その姿を蜃気楼にして、空に映して、砂粒に記憶させたんだ。エム氏は、ただの砂と記憶の砂粒を見分ける名人で、だから考古学者という職業を選んだんだ。ほら」 少年は悲しそうな顔をしてたたずんでいる母親に、ポケットから出した物を見せました。それは青いガラス玉だったのです。母親はしぶしぶとそれを手に取ると、ぶっきらぼうにテーブルに置きました。 「ふん。ただのビー玉じゃないの」 「ビー玉じゃないよ。こんな大きなビー玉なんか、あるわけないだろ」 少年がテーブルに転がっている青いガラス玉に手をのばそうとすると、母親がそれを制していいました。 「さあ。いくんなら、早くいきなさい。帰りには、ちゃんと食べ物を見つけてくるのよ」 少年はちらりとガラス玉に目をやりましたが、思い切ったように勝手口のドアノブをつかみました。 「じゃあ、いってくる」 「キッチンに砂が入らないように、ちゃんと閉めてってね」 ペンキの落ちたドアをするりとぬけると、少年はどこまでも続く赤い砂丘を見渡しました。砂丘の彼方には、赤くドロドロとした「名残りの海」。真っ赤に錆びた熔鉱炉。崩れかけた掘立小屋。たちのぼる紫の煙。海岸の考古学者。結晶した記憶の砂粒…。 「今度のは、どんな化石なんだろう。何が見えるのだろうか」 少年は遥な夢へと一歩静かに歩み出しました。 赤い砂のこびりついた窓ガラスごしに少年を見送ると、母親はテーブルの忘れ物をそっとつまみあげました。朝の光にかざされた青いガラス玉。彼女は何かを思い出したように、その青いレンズに目を近づけていきました。 ※ 1995年 「詩とメルヘン」掲載
ライブラリー バックナンバー クリスタル天文台 海岸の考古学者 春爛漫に送る童話 おはよう ふたりの仕事 パパは世界一の腹話術師 プラモデル1991 バードマンの谷 神様になった慈善家 連休のオフィス モーツァルトを奏でるクジラ達 はいこちら地球防衛軍 戦車 ワリさんリムさん ぼやき漫才
|
| Copyright © emunamae |  |
|